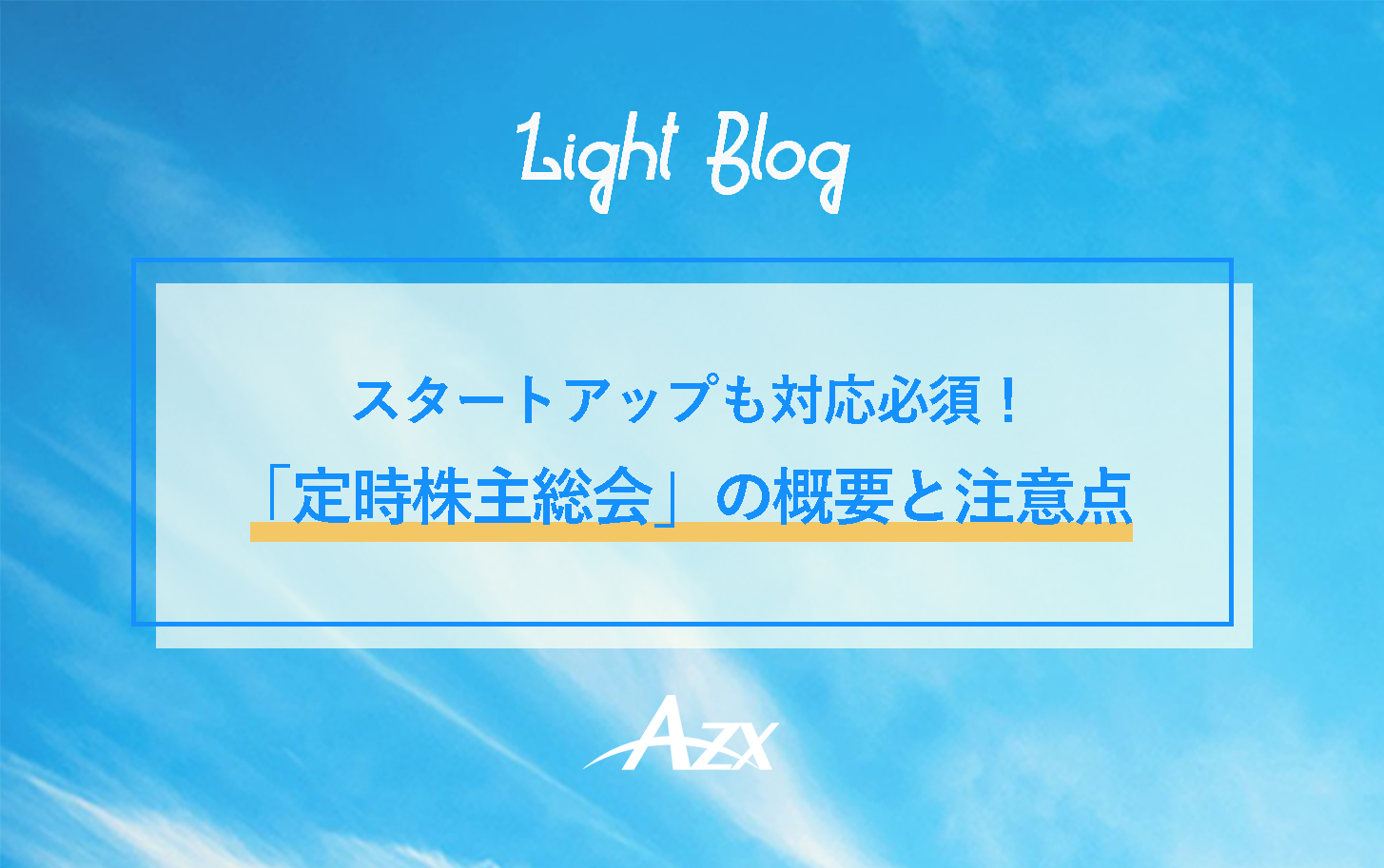
弁護士の平井です。
今年も残すところあとわずかとなりましたが、12月末で事業年度が締まる会社も多いのではないでしょうか。事業年度が締まった後に毎年必ず実施しなければならないイベントが定時株主総会です。上場会社では、定時株主総会は大きなイベントですが、スタートアップの場合は、陰の薄いイベントになりがちです。もっとも、会社の規模にかかわらず、定時株主総会はどんな会社であっても毎年必ず実施しなければならないコーポレートアクションであるため、今回は定時株主総会について解説したいと思います。
1. 定時株主総会はいつ行う?
定時株主総会は、事業年度の終了後3ヶ月以内に実施しなければならないということをご存知の方も多いかと思いますが、実は会社法上は、単に「毎事業年度の終了後一定の時期」に行わなければならないとしか定められていません(会社法第296条第1項)。
ではなぜ、事業年度の終了後3ヶ月以内に開催しているかというと、法人税の確定申告は定時株主総会で承認を受けた計算書類に基づき行う必要があるところ、その確定申告の期限が事業年度の終了日の翌日から3ヶ月以内となっているからです。(厳密には、法人税の確定申告の期限は事業年度の終了日の翌日から2ヶ月以内となっているのですが(法人税法第74条第1項)、会社の定款で定時株主総会の招集を3ヶ月以内に行うことを定めたうえで延長の申請を行った場合には、確定申告の期限を1ヶ月延長することが可能となっています)
そのため、定時株主総会を事業年度の終了後3ヶ月以内に行う旨を定款で定めている会社がほとんどです。
2. 定時株主総会では何を行う?
定時株主総会においては必ず行わなければならないことがあります。逆に言うと、毎年必ず行わなければならない事項があるからこそ、定時株主総会は毎年必ず行わなければならないということになります。
それは、①計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)の承認[1]と②事業報告の内容の報告の2つです(会社法第438条第2項・第3項)。この2つがマストな事項となりますが、取締役や監査役などの役員の任期は定時株主総会と紐づいていることから、その年の定時株主総会で任期が切れる役員がいる場合には、たとえ役員の入れ替えなどがない場合であっても、任期が切れる役員を重任させる重任決議が必要となります(任期が切れた役員には退任してもらい、代わりに新たな役員を選任する場合には選任決議が必要となります)。役員の選任(重任を含みます)を行った場合には、登記手続が必要となるため、定時株主総会を行うにあたっては、任期が切れる役員がいないかを確認する必要があります。
また、会社法上の手続ではありませんが、投資家との投資契約において、役員の選任(又は重任)について決定する場合には、当該決定を行う取締役会決議(取締役の決定)又は株主総会決議よりも前に、投資家からの事前承認等を得ることが必要となる場合もありますので、投資契約を締結している場合には、事前承認等が必要ないかチェックするようにしましょう。
3. 定時株主総会のスケジュール上の注意点は?
会社法上、各事業年度に係る計算書類、事業報告及びこれらの附属明細書(以下これら3つを合わせて「計算書類等」といいます)を、定時株主総会の日の1週間前(取締役会設置会社の場合は2週間前)から5年間、会社の本店に備えおく必要があります(会社法第442条第1項第1号)。
ということは、取締役会非設置会社の場合には定時株主総会の1週間前までに、取締役会設置会社の場合には定時株主総会の2週間前までに、計算書類等を作成しておく必要があるということになります。
そして、取締役会設置会社の場合にはさらにハードルが上がり、計算書類等の内容について事前に監査役の監査を受けたうえで、取締役会で承認を得ておく必要があります(会社法第436条第1項・第3項)。また、定時株主総会の招集通知を送付する際には、取締役会で承認された計算書類と事業報告に加えてこれらに対する監査報告を添付して株主に提供する必要があります(会社法第437条)。(附属明細書を添付する必要はありません)
定時株主総会の開催リミットのギリギリになって、定時株主総会の手続書類の作成をご依頼いただくような場合もあるのですが、上記の会社法上のスケジュール通りに実施するのでは間に合わない場合も中にはあります。
そのような場合でも、会社法を遵守した形で定時株主総会を行う方法が存在します。それは、定時株主総会を書面決議で行うという方法です。書面決議とは、取締役又は株主が、株主総会の目的事項を株主に対して提案し、全ての株主から「同意書」を取得した時点で、株主総会決議があったものとみなす制度です(会社法第319条第1項)。
定時株主総会を書面決議で行う場合には、書面決議の提案があった日から計算書類等を備えおくことで足りるとされていますので(会社法第442条第1項第1号括弧書)、計算書類等の作成がスケジュール上間に合わない場合などには、書面決議で行うことを検討してみてください。
4. 決算公告とは?
定時株主総会の終結後には、遅滞なく定時株主総会で承認された貸借対照表(大会社の場合は貸借対照表及び損益計算書)を公告する必要があります(会社法第440条第1項、会社計算規則第136条)。
公告の方法については、官報公告か電子公告のいずれかの方法を定款で定めている会社が多いですが、官報公告と電子公告では、公告する内容等が異なります。具体的には、①官報公告の場合には貸借対照表の要旨を公告することで足りますが(会社法第440条第2項)、②電子公告の場合には貸借対照表の全文を公告する必要があり、かつ、定時株主総会の終結の日後5年間継続して公告する必要があります(会社法第940条第1項第2号)。
スタートアップにおいては、決算公告を行っていない会社も多く見られますが、決算公告を行っていない場合には、会社法上は、会社の取締役等が100万円以下の過料に処せられる可能性があります(会社法第976条第2号)。
5. まとめ
今回は、会社が毎年必ず行う必要がある定時株主総会の留意点等について解説いたしました。
AZXでは定時株主総会に必要な手続書類の作成や登記手続についてのご相談を日常的に取り扱っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
【脚注】
[1] 会計監査人設置会社の場合には、取締役会で承認され一定の要件を満たした計算書類を定時株主総会に報告すれば足り、定時株主総会で承認を得ることまでは不要です(会社法第439条)。